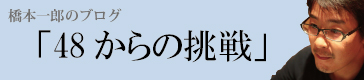Columns|コラムシリーズ8【事業計画の初歩の初歩】全7回
第2回 計画書の構成
前回は「事業計画とは」についてお話しました。
今回は「計画書の構成」についてお話したいと思います。
計画書は大雑把に言うと
・ 狙いまたは目標
・ 施策内容
・ P/L(損益計算書:だいたい営業利益まで)
・ C/F(キャッシュフロー)
で構成されます。
だいたい法人の場合、会計年度は1年間で規定されることが多いので、
ここでも1年間の活動という前提にします。
狙いを定めて、その狙いを実現するための具体的な活動内容を定め、
その結果どんなP/L、C/Fになるかと計算します。
1回の検証でこれがピタリとくることはまずないです。
「あれ?全然利益が足りない」とか「売上が達成できない」とか、
定めた狙いに届かないことがあります。
となるともっと前提条件を厳しくするとか、
活動を増やすとか、中身を変えるとか、
「施策内容」をまた見直します。
時には定めた狙いが現実離れしている可能性もあり、
そこから見直すこともあるでしょう。
逆に簡単に目標達成が実現できそうな場合、
自分の事業としてそれでいいのか、
という自問自答があります。
目標が低すぎる?いやいやこれでいい?
ではそれぞれ見ていきましょう。
【狙いまたは目標】
1年間活動してどうありたいかを自分で定めるところです。
自分の意思が最も反映されるところですので、じ〜っくり考えましょう。
オペレーションの視点でいけば、
「事業を開始する」とか
「売上をこれくらいの規模にする」とか
「利益をこのレベルまで実現する」
「固定客をこれくらい確保したい」といったことが指標になります。
まだ売買の段階でない場合、立ち上げ環境を整える、というのも大切なステップです。
「資金をどれくらい集めるか」
「メンバーをこれくらいまで集める」
「設備をここまで整える」
こういったことも目標になるでしょう。
私の場合、「シェアハウスの管理運営」という事業をするにあたり、
・ 1年目はまず1棟の運営を開始する
・ 2年目は複数棟の運営を行う
・ 3年目は違うコンセプトを開発する
・ 4年目以降に新規事業を立ち上げる
といった目標をたてました。
漠然ですけど最初はこんなもんでいいと思います。
【施策内容】
目標をたてたらそれを実現するための行動計画です。
どんな行動をとっていくのか具体的であればあるほどいいです。
たとえば「売上を◯◯まであげたい」という目標を立てたとします。
売上は「単価x個数」ですから、単価と個数の前提を設定することです。
目標を「売上100万円達成」と設定したとしましょう。
提供するサービスは競合や市場を調査すると10,000円が競争力ありそうだとします。
ここで単価の前提を10,000円とします。
目標を達成するには100単位販売する必要があることがわかりますね。
すると次は100単位販売するための施策を考えます。
販売だから誰が(あるいは何が)販売するのか。
自分が直接販売するのであれば何単位売れそうか。
ネットを使って何単位売れそうか。
事業経験があれば、それぞれの販売チャンネルで
どれくらい販売できるのかある程度予測をつけられます。
この顧客ならこれくらい買ってくれそうだ、とか、
新規顧客はこれくらい増えそうだ、といったように。
ところが事業始めたばかりのときはそうはいきません(^^)
経験値がないので「これくらい」という感覚がないからです。
私も正直わかりませんでした。
私の場合設定する前提は「物件の調達」「集客」という2つの面で施策、前提が必要でした。
物件調達についておいた前提は
・ 物件は建築事務所から紹介してもらう
・ 部屋数、平均賃料、平均入居率
でした。どれも経験がないので根拠が乏しいです(^^)
集客の前提は
・ Facebookで広告をうつ
・ Facebookでつながっている人に紹介してもらう
・ ビジネススクールの学生にアプローチする
というごくごく曖昧なものでした。
でもいいのです。
完璧でなくてもまず前提条件を設定することが大切です。
【P/L】
そして数値化します。
損益計算書をP/Lとよくいいます。
簡単にいえば、どれだけ売り上げてどれだけ経費をかけて、
どれだけ利益がでたか、を表しているものです。
売上—経費(変動費)—経費(固定費)=営業利益
これが簡単な図式です。
簿記やアカウンティングを勉強した方はおなじみだと思いますが、
実はビジネススクールの学生でもこのあたりが苦手という人は少なくないようです。

次回からこのP/Lの中身について私の事例を交えて紹介していきたいと思います。