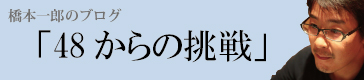Columns|コラムシリーズ10【ものづくりに見る価値の創造】全10回
第5回 それぞれの役割〜製造
前回までに“基礎研究・開発”、“設計”についてご紹介しました。
今回「商品化」する商品を生産する“製造”についてお話します。
“製造”は役割を分担して分業体制が一般的です。もちろん始めから最後まで一人で担うものをあります。
職人が作る陶芸や1人で切り盛りしている食堂などです。
ここでは一般的な例として分業化した“製造”についてご紹介します。
“製造”は
・ 生産の計画をたてて
・ 計画に沿って材料を仕入れて
・ 材料を加工・組み立てて梱包し
・ 品質を確認し
・ 出荷する
という作業を行います。
同じ商品を大量に生産する場合同じ作業をひたすら繰り返すことで習熟度があがり、生産性をあげることができます。
同じ作業をしていると段々なれてきて早く終わらせられますね、それです。
“製造”が分業化される傾向にあるのは「大量に安価で安定的に」生産をする上でその体制が向いているからです。
役割ごとに組織を当てはめてみると以下のようになります。
・ 生産計画:生産の計画をたてて
・ 資材調達:計画に沿って材料を仕入れて
・ 製造:材料を加工・組み立てて梱包し
・ 物流(ロジスティクス):出荷する
これに加えて、共通部署として
・ 製造技術:製造用設備、治具を開発・設計
・ 総務・人事
といった部署が存在します。
“製造”は身近な所では料理に例えるとわかりやすいかもしれません。
・ 生産計画:1週間の献立を考える
・ 資材調達:食材をスーパーに買いに行く
・ 製造:料理をして盛り付ける
・ 品質管理:味見
・ 物流:食べる人の時間に合わせて配膳
こんなところでしょうか。
献立を考える時は中身もさることながら、作り過ぎも少なすぎも行けないので予算に応じて必要量を考えなければなりません。
“製造”における生産計画の肝はここです。十分かつ過不足なく、が大切なのです。
少なければ販売が減ってしまうので論外ですが作りすぎるとそれが在庫となって、お金を投じたのに売れない事になってしまいます。
100万円の現金があるのに使えない状態ってこまりますよね?実は“製造”の財務面において生産計画は大切な柱の1つになります。
献立ができたらお買い物です(^^)作るものと量が決まっているのでそれに合わせて材料を仕入れます。
いつものスーパーで野菜がいつもよりも高い時、他のスーパーで安い野菜を調達したりします。そんな役割も資材調達は担っています。
ある部品メーカー、材料メーカーが高い、量が不足するといった時代替メーカーから調達をするのです。
さあ、材料がそろって調理、すなわち製造です。食材をカットして下ごしらえして火にかけます。この時に大切なのは「段取り」ですね。
いろいろなことを並行して効率よく作業を進めます。実際の製造では作業が「工程」と呼ばれる区分に細分化されます。
これら工程の流れるバランスとスピードが生産性に大きく影響します。
品質管理のプロセスでは料理のケースとちょっと合わせにくいのですが本来の機能が発揮されているか汚れやキズなどがないか、といった出来上がりを確認するところです。
ここで悪いものが頻発すると「作り方がおかしい」として生産を止めるという強い権限をもっています。
品質の悪い製品は出荷しない、というスタンスですね。
めでたくチェックに合格した商品は倉庫を経由してオーダーをいれてきた顧客や自社の販売倉庫に運ばれます。
ここまでが製造の流れになります。
基礎研究・開発が試行錯誤しながら進めていくのに対し製造ではやることが明確に定義されています。
安定的に画一的に生産をしていくためです。ものを置く場所なども明確に規定されています。
「〜〜べき」という言葉をよく聞くのは正しい手順に従って作業をすることを求められている裏返しなのです。
従ってやることが明確にされ整理整頓が行き届いている現場は、いい製造所だな、という印象を持ちます。
私がお世話になった製造所の方が、製造のミッションについてこうおっしゃっていました。
「製造のミッションは納期を守ること」これって指定した時間に届ければいい、という単純なものではありません。
製造の役割がぐっと凝縮して前提として存在しているのです。
「納期を守れた」ということは
・ 指定された商品である
・ 要求された数量を生産できている
・ 期待されている品質を守れている
・ 約束された価格を実現できるコストを守れている
という前提があるのです。
この言葉を製造のミッションとして引用させていただきます。

次回は「販売」をご紹介します。