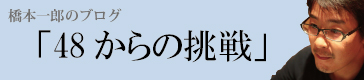Columns|コラムシリーズ10【ものづくりに見る価値の創造】全10回
第10回(最終回) ものづくりから学んだこと
これまでいろいろな側面から“ものづくり”をご紹介してきました。私は前職が“ものづくり”のメーカーだったので仕事や事業にかかわることのほとんどを“ものづくり”から学んできました。
製品を出すために多くの役割があること。
その役割に沿って組織が編成されること。
安く作って高く売ることで利益が生まれること。
ルールや規格、仕様といった決め事には理由があること。
習熟していくということ。
手順があること。
データはばらつくこと。
データの解釈によって結論がかわること。
良い物つくればいいというわけではないこと。
技術は嘘をつかないこと。
お金がかかること。
優先順位があること。
海外が食わず嫌いだったこと。
英語が使えなくても意思疎通は可能なこと。
事業相手が法人であっても会話している相手はヒトであること。
アウトプットを出して初めて仕事したと言えること。
他責では進展がないこと。
人それぞれ感情があり得手不得手があること。
誠実であること。
約束は守らなければならないこと。
会社を退職してビジネススクールに通い経営学を学びました。その際にも“ものづくり”の経験がその学習に大いに役に立ちました。
“ものづくり”の経験がなければいけないわけではないですが、その経験によってプラス面が多くあったと感じています。その学びがあったので今の事業につながっています。
シェアハウス運営事業と“ものづくり”は直接的には無関係に見えます。確かに当時学んだ技術の話はシェアハウス運営には全く使っていません(^^)
有形の物を作っているわけでもありません。でもサービスを生み出して提供していくという流れは“ものづくり”でいう開発から製造の流れと合致するのです。
ヒトを相手に仕事するスタイルも同じです。かける経費をおさえつつ売上を上げるという事業構造も同じです。いろいろな面でスタイルがつながっているような気がします。
“ものづくり”は投資も大きく制約もいろいろあり限られた自由度の中でパフォーマンスを出すことが要求されます。
そういう一種の制約があったからこそ私のような性格の人間はトレーニングになったのかもしれません。仕事を進める型のようなものでしょうか。
今回のシリーズが“ものづくり”に対して少しでも理解の助けになれれば幸いです。

次回は新シリーズです。